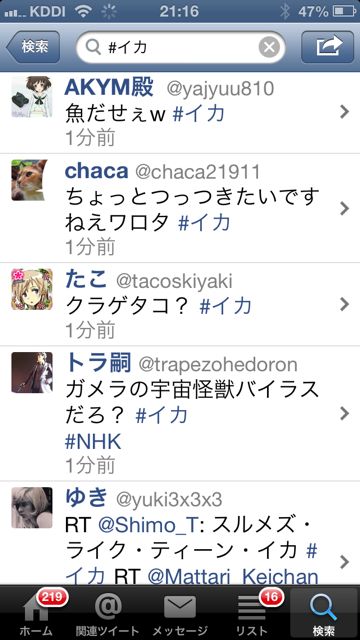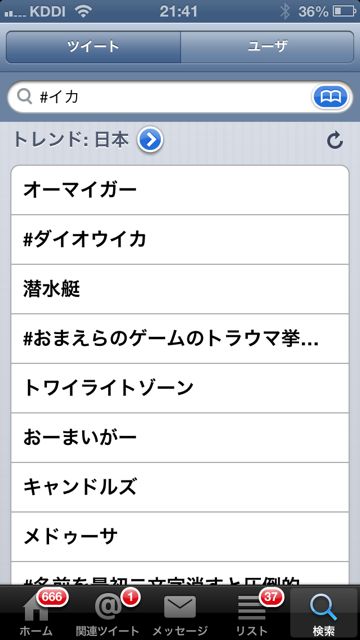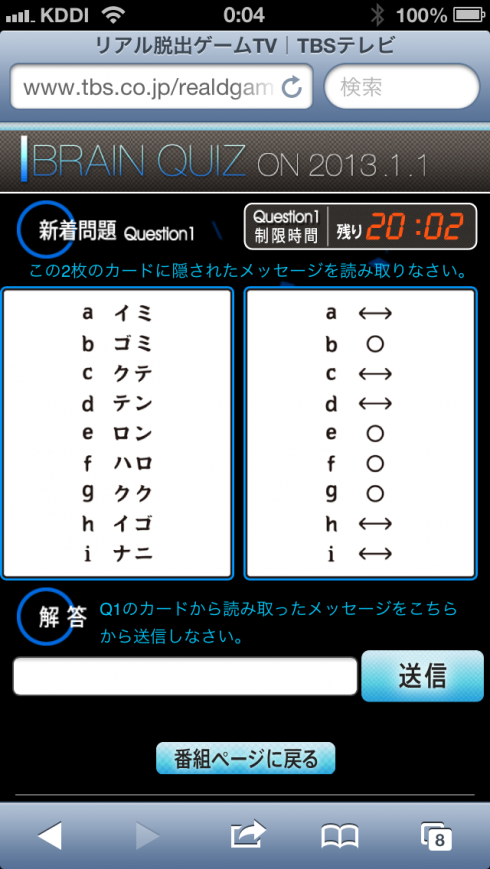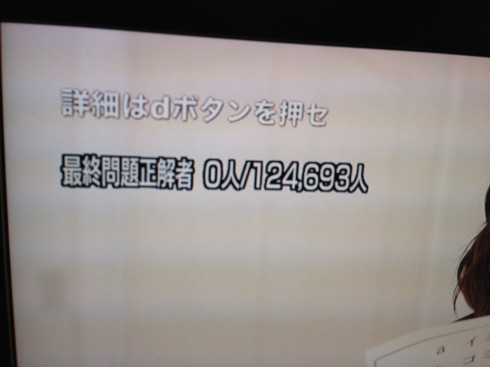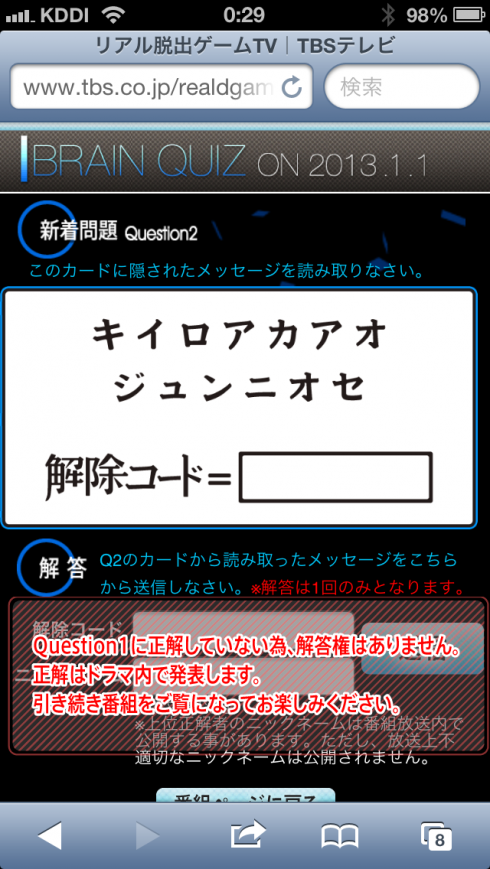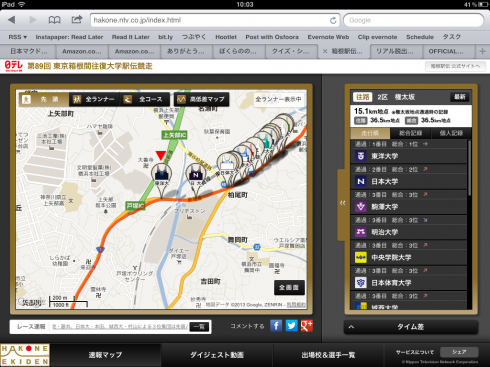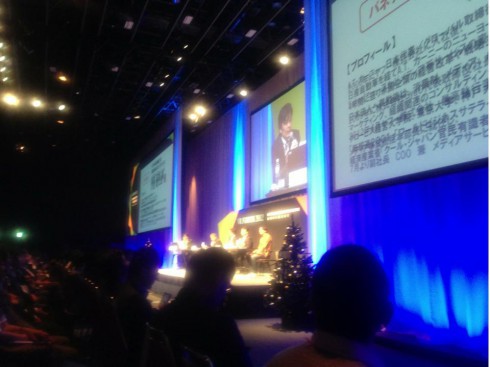今回の選挙の結果についてとくに言いたいことはない。投票率が低かったことについてだけ言うと、当然だと思う。もちろんぼくは投票に行ったが、こと今回の選挙では投票しなかった人をとやかく言う気になれない。あの党が勝つのはイヤだけど、だからって他のどこに入れればいいのか。今回の選挙は、この国がいま、ただのカオスになってしまっていることを象徴していると思う。村上龍の「愛と幻想のファシズム」みたいな世の中になりつつあると思うと、おそろしい。
それはともかく、選挙はおいといて、”政治“にからんで経験したことと思う所を書こうと思う。
これは前職ロボット時代の話。別に秘密にすることではないと思うので書いちゃうと、ロボットの社員がアカデミー賞をとったことがある。加藤久仁生というアニメーション作家の「つみきのいえ」という作品が、2009年の米国アカデミー賞短編アニメーション部門で受賞したのだ。もちろんロボットはお祭りのような騒ぎとなり、みんな自分のこととして大喜びした。
ぼくは経営企画室長だったので、外部への対応で毎日大変だった。大変だけど、うれしかったので、大喜びしながら対応に追われるというマゾヒスティックな日々となった。まさか自分の会社の人間が、あの世界的な賞をとるとは思わなかったからね。
世界的な賞をとると、いろんなところが注目してくれて、経産省からも電話があった。加藤さんを大臣に会わせてねと言うのだ。で、当時の阿部社長とともに霞が関まで加藤くんを連れて行った。この時は外国語映画賞の「おくりびと」とダブル受賞だったので、滝田洋二郎監督も呼ばれていた。
招き入れられた部屋は中規模の会議室で大きなドーナツ状の円卓が真ん中にあった。ぼくは事務方としてその周りの椅子に社長と一緒に座った。するとそこへ、またいろんな方々がやって来た。映画製作者連盟を代表して東映の岡田社長、レコード協会、動画協会、などなどお歴々が顔を並べる。うーん、これはなんだ?そこに、当時の経産大臣、二階さんがやって来て、滝田監督、加藤監督と挨拶して握手。大臣はすぐ退席して、経産省の局長クラスとそのメンバーの懇談的なミーティングになった。話の内容は、各業界からの直訴的な。
連絡をくれた経産省の方によると、各業界団体と局長との懇談会の場があって二階大臣も顔を出すので、いい機会だと両監督を呼ぶことになったのだとか。ぼくは、業界団体のロビー活動の場に世界的な賞をとった監督を呼ぶのはいかがなものかと軽くクレームを言った。
ただこの時、業界団体の意味がよくわかった。そういうことなんだな。○○協会とは、インナーより対外的、そして政治的な存在意義があるのだなと思い知った。
さらに一二ヶ月後だったか、今度は首相官邸から連絡を受けた。内閣として、ジャパンブランドを海外へ売り込むプロジェクトがあり、その報告会が官邸であるので加藤監督をお招きしたい、とのこと。経産省の経験があるので、またついでに呼ばれるんじゃイヤだと思い、もっと詳しく聞かせてもらった。今度は会合のゲストとして意見をお聞きしたい、社長もぜひにと言うので、経産省の時よりいい立場で呼ばれるのだなとお受けした。
ロボットを紹介する映像も準備したり、社長が話す内容を官邸の方と下打合わせしたり、それなりの準備をした。
ジャパンブランドについての会合はまたもやいろんな業界のお偉方や政界に強い某出版社社長、高名な大学教授などで構成されていた。その日は、彼らが大臣達の前で進捗を報告し、その中でアカデミー賞受賞を本人から伝えてもらうというものだった。官邸の方とお話して、社長からぜひコンテンツビジネスについて大臣達に語らせたいとお願いした。
加藤監督がアカデミー賞受賞を報告し、授賞式でのエピソードなども軽く話した。そのあとで、阿部社長からコンテンツビジネスについてアピールした。皆さんはテレビ局や配給会社が作っているとお思いでしょうが、実際の現場はその奥にいる我々制作会社が作っています。でも零細企業です。その中から運良く世界的賞を受賞できました。どうぞ我々の存在にも目を配ってください。そんな話をした。ぼくが原稿を用意したのだが、阿部社長は原稿から話がそれてハラハラしたが、でも言うべきことはちゃんと言ってくれた。
麻生首相はマンガ好きでぼくらのバックアップしてくれそうだった。でもあっさりその夏の選挙で下野してしまった。
この頃すでに、ハリウッドと日本のコンテンツビジネスの違いについては認識していた。米国にはフィンシンルールという、制作者を有利にする法律がある。あれはどう見ても、ハリウッドがテレビ局の力を抑えるために作らせたものだ。ロビー活動の成果だ。
経産省や官邸に接してみて、日本でもロビー活動をしなきゃいけないなと思った。だって配給会社やテレビ局はやってるんだろう?プロダクションもやらなきゃ。それも、既存の枠組みの業界団体ではダメなんじゃないか。映画だテレビだCMだの枠組みを越えて大きく結びつかなきゃダメなんじゃないか。
これを痛感したのも「つみきのいえ」の受賞時だった。世界的な賞をとったのに、海外に上手に売れなかった。売り方を知らなかったのだ。賞をとったからさっそく世界で売れるかというと、そんなに単純じゃない。世界中から「うちの国で売るなら、おれだから」というメールが来たのだけど、どの事業者がホントに頼もしいのかわからない。日ごろから情報収集や人脈形成していないと、海外セールスなんかできないのだ。
でも、ロボットは制作会社の中でも大きい方だけど、それ専門の部署なんかつくれない。3年間専念していいから海外販路を開拓してくれ、なんてできないんだ。
もっとまとまらないといけないし、政治の助けも借りないわけにはいかない。そう思って、ぼくはそのあとも、内閣官房や経産省、総務省にも行ってどんな人が絡んでいるのか動いて回った。
でも阿部社長が辞めたり、自分も辞めたもんで、中途半端に終わってしまった。
日本のコンテンツ界の大きな欠点がある。それは、制作者主導じゃないことだ。まず、テレビ局、配給会社という、言わば流通企業が業界の顔になり政治に向いている。その先にいる制作者の視点ではない。これは会社単位で見てもそうなのだけど、会社の中でも、例えば総務省の会合に出るのは制作部門の人ではないだろう。そこで語られるのは、電波利権の確保の話であって、いいコンテンツを作る環境の問題やコンテンツを海外セールスする話にはならないのではないか。
外側の話だけを行政として、肝心の内側、アンコというか具の話は政治の話になっていない。ほとんどなっていないと思う。
制作者がもっと表に出て、政治の話やビジネスの話をしないといけない。そうしないと、制作者が生み出したものの価値を高める議論にならないのではないだろうか。