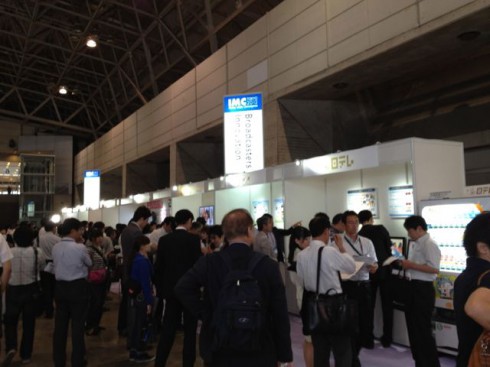7月15日の境塾でゲストにお招きする小寺信良さん。コラムニストであり映像技術者でもあり。「金曜ランチボックス」というメルマガを発行していて”夜間飛行”というメルマガサービスで購読できる。ePub形式でも読めるので便利だ。
そして小寺さんは津田大介氏とともにインターネットユーザー協会、通称MIAUを設立し代表理事を務めている。このMIAUを設立した背景をお聞きしたことがある。
インターネットでの著作権に関して意見を言うには、個人では受け入れてもらえない。業界団体はいろいろあって彼らは著作権改定の議論に参加できる。すると、業界団体の論理だけが反映されていく。ユーザーの声は反映できないのだ。反映させようとすると消費者団体が関与することになり、消費者団体は主婦の声の代弁者だからネットのことなんかわからない。
だったら自分たちでユーザーの声を代弁した団体をつくろう!
そこで生まれたのが、MIAUだった。
ユーザー団体をつくったらちゃんと、著作権に関する議論に参加することができた。「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」という本がある。この中に、著作権改定に関する議論のレポートが書かれていて、多様な著作権者側の団体と”闘う”津田氏の様子が出てくる。これを読んでいると、”日本の著作権がなぜこんなに厳しいのか”がよくわかる。権利者団体側がとにかくひたすら”守る”立場を主張するので、そしてそれを全部聞き入れていこうとするので、法律がどんどん頑なな方向に向かっていくのだ。
”違法ダウンロード罰則化”という問題がある。インターネット上にある音楽・映像ファイルの中で違法にアップロードされたものをダウンロードしたら違法になる。これは、映画館で本編上映前に”NO MORE 映画泥棒”というCMで、後半で訴求されている。女の子がニコニコしながらパソコンで音楽をダウンロードしていると”ブーッ”と警告とともにポリスマンが現れる。あそこで指摘されていることだ。
ただ、いままでは違法ではあっても罰則がなかった。今回の著作権法改正で、これに罰則を加えようという条文が入っているのだ。罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。これはマジな罰則だ。
MIAUはこれに対して議員向けの反対声明を発表している。この機にぜひじっくり読んでほしい。このまま法律が通ると、よくわかっていない子供たちが刑罰の対象になるし、濫用されるとパソコンを突然のぞかれたりする、この問題はじっくり議論する必要があるよ、そんなことを言っている。
注意すべきなのは、決して「ダウンロードしてもいいじゃん!」とは言っていない点だ。慎重に議論しようよと言っている。しかしこの法案は、6月15日に衆議院であっさり可決されてしまった。議論は参議院に移っていく。
昨日、6月19日の午後、参議院で参考人質疑が行われ、その模様をニコニコ生放送で中継されていた。たまたまヒマだったので、かなりの部分を見ることができた。見てない人もITmediaのこの記事を読むとだいたいわかる。
記事を読めば、誰がどんな立場で何を言ったかはだいたいわかると思う。反対の側の参考人のひとりが津田氏だった。いつもながらうまく論点を整理してわかりやすく話す。中でも説得力があったのが、「罰則化するとユーザー側が萎縮して音楽を買わなくなる」というもの。確かにそうだろう。萎縮もするし、反発も出るかもしれない。そんなに聞くなってんなら、いいよ、聞かないよ。ぼくの高二の息子なんかそんなこと言いそうだ。
参考人の意見陳述がひと通り終わると、議員からの質問コーナーになった。森ゆう子さんという議員をぼくはよく知らなかったけど、彼女の質問が面白かった。改正案に賛成の立場の参考人として岸博幸という元官僚の大学教授が出ていた。ぼくははっきり言ってこの人が嫌いなんだけど、この日も音楽産業側の立場で話していた。
森議員が岸氏に質問した。「フランスで罰則化が行われていますが、かの国では音楽産業の収益は上がったのでしょうか」これに対し岸氏は「音楽産業のデータは持たないがiTunesの売上はあがっているはずだ」すると森議員「深く調べたわけではないが手元のデータでは数%の減少となっている。罰則化しても売上があがらないのでは意味がないと思う」岸氏は「音楽の売上は様々な要因が作用するので一概に言えない」・・・うーん、岸さん、苦しいよ・・・
そうすると、MIAUの主張である「慎重な議論が必要です」がまったく正しいということだろう。音楽産業がどんどん売上が下がっている、それは違法ダウンロードが横行しているからだ!ぶっちゃけ罰則化のモチベーションはそこにあるはずだ。でも罰則化を先にやっている国で売上が下がっているなら、効果がないと言うことだ。
ことはそう、単純ではないのだ。
いま言える正しい答えは、”慎重に議論すること”なんじゃないだろうか。
著作権とは、20世紀的な概念だと思う。大量生産大量消費と、マスメディアと、そして複製する重厚な設備が掛け算して行く時に必要な概念だった。ポイントは、複製をつくるにはそれなりの金額の設備投資が必要だった。
21世紀のいま、複製は限りなくカンタンになり、コストも限りなくゼロに近づいている。そんな中で20世紀と同じ著作権でいいはずはないのだ。無理があるに決まっているのだ。そして往々にして時代が変わる時、正解は変わる方に一緒に動くことなのだ。”おれたちには権利があるんだ”と言い続けていても、オールドメディアとともに崩れ去るだけだろう。
なんて小難しいことも言ってみたりしつつ、7月15日の境塾に参加して、一緒に考えてみようよ、と呼びかけてみたりもしよう。コンテンツと著作権について考えてこられたお二人にいろいろお聞きしつつ、あなたも考えてみようぜ。お申込はここをクリックして、ATNDから登録してくださいな。待ってるぜ〜!