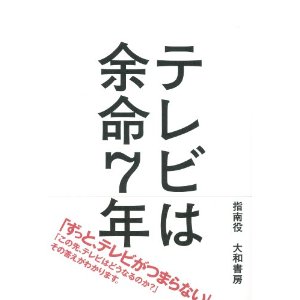今週は、幕張でCEATECをやっている。そう言えば、去年のこのブログでも「GALAPAGOSには期待しちゃう」という記事を書いた。実際、去年のSHARPの展示にはコーフンしたんだよねー。でも、皆さんご存知の通り、GALAPAGOSは・・・(‘_;)
それにもめげず、今年も張り切って幕張に行った。今回は”出演”もあったのだ。ISDB-Tマルチメディアフォーラム主催のパネルディスカッションに呼んでいただいたのだ。
というか、ようするにmmbiのデモンストレーション的な催しなのね。
mmbiって何?えーっと、これ説明すると長くなるので、別の機会にじっくり書きます。なんだい知りたいよ、って人は、自分でググってみて。アナログ停波後にあいた電波でドコモの出資した新会社が新しいサービスを始める。蓄積型放送サービスという、新業態らしい。ここではそれくらいにしましょ。
そのパネルディスカッションのために幕張まで行ったのだけど、せっかくだし、いろいろ回った。で、なーんか去年と違う気がした。
そもそも、展示のスケールダウンを感じた。去年はところせましと各ブースが張り切って並んでいて、歩くのが大変だった。今年は、実にスムーズに移動できた。ブースも減ったし、来場者も減ったんじゃないかな。
そして、テレビの展示が減ったと思う。
CEATECは総合エレクトロニクス展示会だから実に多様な事業者が多様な製品やサービスを展示している。でもそんな中、”やっぱりメインはテレビだよね”という空気があったと思う。トリというか、締めというか、花形というか、が、テレビだった。
でも今年は違う。テレビの面積というか割合というか、少なくなった。あ、もちろんテレビもやってますけどね、でもこれまでほどのスターでもないんですね、すみません。そんな感じだった。
いろいろ見ていく中で、東芝のREGZAのブースに行った。おやー?なんだか面白そうだな、スマートテレビと関連アプリ?えーっと誰か説明してくれるかなー・・・と、見回したら、片岡さんがいらっしゃった。
片岡さんは、東芝のスマートテレビ関係の開発の中心人物で、その関連のセミナーなどによく登壇される。そしてこないだ、慶応大学メディアデザイン研究科主催の”スマートテレビ研究会”の会合があって、なぜかぼくも呼ばれ、片岡さんは当然参加しておられた。
大勢の会合でご挨拶できなかったのだけど、つかつかと寄ってきてくださって、説明をしていただけた。片岡さんは相当な立場だと思うのだけど、”説明員”の札をつけてひとりのスタッフとしてブースにいる。うーん、”そういう”方なんだろうなあ。
さすがにREGZAはテレビ、ブルーレイレコーダー、そしてタブレットとアプリ、それらが細かに連携してユニークなサービスを提供している。スマートテレビの中でもいちばん進んでいると言えるかもしれない。
いろいろ見た中でいちばん驚いたと言うか、新体験な気分を感じたのが、タブレットとブルーレイレコーダーの連携プレイ。
テレビ放送を、ブルーレイレコーダーのチューナー経由で、タブレット上で視聴できるのだ。・・・え?タブレットでテレビが見れるのね?・・・それが何か?・・・と、言葉で説明されるとそんな”大したこと”な感じがしないだろう。
でもね、百聞は一見に如かず。実際にタブレット上でテレビ放送を見る、というのは、新鮮で不思議な感覚になるんだ。盲点というか、意外や意外!
そして、ぼくはそこにこそ、”放送と通信の融合”の真の姿があるのでは、と思ったの。タブレット上で放送を視聴し、何か気になったりしたら、ネットにパッと切り替えてWEBブラウズしたりね。これは、発展するとテレビから直接ECサイトに、という流れもできちゃうのだろう。
・・・あ、まだピンと来ないね?そうだよね、わかりにくいよね。・・・そっか、写真でも撮っておけばよかったんだよね。・・・うん、よし!CEATECにはもう一度行く予定だから、写真撮ってこよう、うん!・・・というわけで、次回もCEATECの話になりまーす!
関係ないよで関係あるのが、10月14日開催の、BAR境塾。ソーシャルアプリを開発した方々とトークイベントを行います。申し込みはこちらをクリック。30名の枠が、だんだん埋まりつつあるので、お早めに!