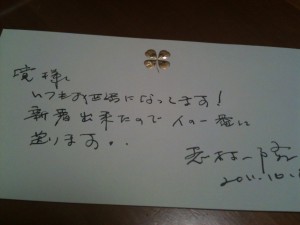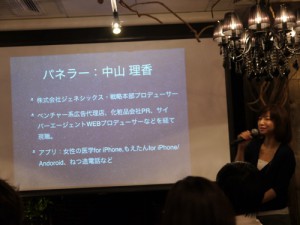ジョブズの訃報を聞いてから、ずっと自分とMacについて考えている。
ある人から「Macに救われました」とTweetをもらったことがある。その時ぼくは確か、それは大げさでしょう、てなことを返した気がする。でも、自分を思い返すと、全然大げさじゃないなあ、と気づいた。
ぼくは93年に代理店を辞めた。いきなりフリーランスになったのではなく、実は半年ほど、あるデザイン会社にいた。いずれフリーになるつもりで、まずはそのデザイン会社で新たな経験を積もうと思ったのだ。
ぼくは部屋をもらい、そこにはパーソナルコンピュータが置いてあった。虹色リンゴのマークがついていて、Macintosh Classicと書かれていた。気の利いたデザイン事務所が”マック”と呼ばれるコンピュータを導入していたのはなんとなく知っていた。でもそれを自分が日々使うことはイメージできていなかった。
代理店にいた時からワープロは使っていたので、キーボード入力で画面上で文章を書いていくのは違和感がなかった。ただ、”イラストレイター”という、ワープロとは別のアプリケーションを使ったのは新体験だった。そのデザイン事務所では、キャッチフレーズを打合せで決めたら、それをMac上のイラストレイターで打ち込んで、プリントアウトしたものをデザイナーに渡すのだ。
キャッチに続く説明文(ボディコピー)もイラストレイターで打ち込んでデザイナーに渡す。それだけで、デザインチームにとってはかなり作業が楽になるのだという。
ぼくはそういう、新しい機器をいじるのは好きだった。だから、毎日そのMacをさわっては、いろんな使い方を見いだしていった。
そのデザイン事務所は半年ほどで辞めていよいよフリーランスになった。さらにその半年後にいよいよ自分のMacを買った。その手に詳しい友人に新宿のソフマップにつきあってもらい、わりと廉価な機種を買った。Performa588というマシンだった。
コピーライターの最重要な仕事は、キャッチフレーズ案を提案することだった。代理店にいた頃から、A4の紙にひとつひとつのキャッチ案を書いて打合せに持っていっていた。ぼくは字が下手だし、文字を適切にA4の紙に配置するのは意外に難しい作業だった。
十数文字のキャッチフレーズをA4に書くと、どうもバランスが悪かったり、行替えがまずかったりして、何度も書き直したりした。
Macを買ったら、キャッチフレーズ案もMacで書いてプリントアウトして打合せに持っていくようになった。書き方も徐々に進化させ、キャッチフレーズをどんとレイアウトし、その下にショルダーフレーズと商品名をびしっと置く。すると、その広告の構造がひとめでわかり、そのキャッチフレーズが持つ企画性も伝わりやすかった。
コピーライターはアナログな人種で、ぼくも本質的にはそうなのだが、90年代前半にMacを使いこなすコピーライターは少なく、なんとなく”進んだ人”という見え方でトクをしたと思う。
また、コピーライターはコピーだけ提案すればいいわけではない。むしろ、コピー案に至る前の企画意図やコンセプトワーク部分が重要だったりする。そこでぼくは、Macを駆使して対象となる商品をどうとらえ、どんな考え方でメッセージを組み立てるべきかを説明するのにも使った。文章だけではなく、図やチャートもうまく使った。
また、コピー案だけでなく、ビジュアル案もセットで出した方が企画がはっきりして説得力が出る。そこで、スキャナーで雑誌や写真集のビジュアルを読み込み、イラストレイターでキャッチ案とともに配置してプリントアウトしたものを打合せに持って行った。
そうすると、クリエイティブに至る背景の説明から、アウトプットの具体まで、ひとりで考えて打合せに提示することになる。そういう企画の出し方をすると、打合せのイニシアチブをとることができた。代理店やプロダクションの人も、この男は便利だぜ、ってことで頼りにしてもらえた。
マシンもどんどん買い替えた。PowerMac7300とモニターを買い込み、Performa588は子供たちのおもちゃになった。PowerBook2400cを買ってからはどこへでも持ち歩いた。喫茶店でボディコピーを書き上げたりしたものだ。PowerMacG3 DT233を買ってCPUやHDDの換装をやってみたりした。588が逝ってしまいiMacを家族用に買った。PowerMacG4が登場したら早速買いiMacのフラットパネルモデルが出たら面白がってすぐ買った。
基本的にワープロと企画書が使えればいいので、最新機種を追いかけて買う必要はまったくなかったのだが、最新機種を追いかけた。でもその中で、廉価なモデルを買った。それで十分だったからだ。最新の性能が必要だったのではなく、最新の機種を手元に置きたかっただけなのだ。
最初の頃のMacはよくフリーズした。昔は”爆弾マーク”が画面に出てきた。重要な企画書をノって書いてる時にフリーズして、マシンをあやうく投げそうになったことが何度もある。腹は立ったが、システムフォルダの中をチェックし、機能拡張書類をはずしたりなど工夫することはまた楽しかった。徹夜でフリーズの原因を究明し、朝方からようやく企画書にとりかかって寝ずに間に合わせたこともある。
そういう苦労も、Macで仕事する楽しさのひとつだった。
とは言え、MacOSXになって圧倒的にフリーズが減って、やっぱりうれしかった。それにOSXの先進的なインターフェイスや垢抜けたグラフィックスはMacの魅力を倍化させた。
時折、Windowsマシンを買ってみたりしたけど、全然使いにくかった。使われているフォントも好きになれなかった。全体的にグラフィックスが鈍くさいと感じた。
Macは”好き”だった。”好き”の塊みたいなものだ。人間が中に住んでいるんじゃないかと思えるような、ヒューマンなムードを持っていた。
こんな風に、Macを手にして、Macとつきあい、Macを愛してきた人は世界中にいっぱいいるんだろう。そして、それぞれの創造性を形にしてきたんだろう。Macを通じてどう創造的な作業をするか、それぞれ工夫したはずだ。その工夫がまた創造的な作業だった。
ジョブズがいなかったら、ぼくたちはどうなっていたのだろう。いや、Macは、そもそもAppleのコンピュータは、ジョブズの発明品ではない。Appleがはじめてパーソナルなコンピュータをつくったのは、同じスティーブでも、ウォズニアックのおかげだ。Macintoshを特徴づけ、やがてWindowsにも受け継がれたGUIとマウスによる操作は、XEROXの研究所が開発したもので、それをジョブズがパクったのだ。
でもジョブズは、GUIとマウスの先進性、必要性に気づいて、Macintoshに採用した。ジョブズがそうしなかったら、XEROXの研究者たちの成果は上層部に否定され日の目をみなかったろう。そうしたら、パーソナルコンピュータは理系オタクな人々だけのモノであり続けたのかもしれない。
そしたらぼくは、独立後もずーっとA4の紙にキャッチフレーズを手書きでまとめようとし続けたのだろう。企画書も誰かに清書してもらわねばならなかったかもしれない。何より、Macという不便なマシンと格闘したり新機種が出るたびにワクワクしながら買うべきか悩むというあの楽しみはなかったのだ。
そんな仕事のやり方はさぞかし大変だったろうし、そんな人生はさぞかしつまらなかっただろう。
そうだ、ぼくの人生がここまで楽しかったのは、ジョブズがXEROXの研究の成果をパクってくれたからだ!
ジョブズがそんな詐欺まがいのパクりを平気でできたのは、彼が信念を持っていたからだ。彼は技術者ではなく、メッセンジャーなのだ。
彼の死後、あちこちのニュースサイトやブログから聞こえてくるのは、彼の言葉だ。たくさんの言葉を彼は世界に発信し、その言葉に基づいた製品を世界に送り出した。そのおかげで世界中の人々が、自分の人生を切り開くことができた。
”ほら、思いついたことを何でも形にできるマシンをつくったよ。これを使って、君はなにをしたっていいんだ。どう使うかは、君の自由だ。やってみてごらんよ。君はもう、何だってできるはずだよ。”
十数年前、パッケージからとり出したPerforma588はぼくに語りかけてきた。そのメッセージは、2011年の機種でも変わらない。iPhoneやiPadも同じメッセージを言う。
Appleはこれからも世界中の人生を救うのだろう。スティーブ・ジョブズという人物が生まれてきて、人類は本当に良かったと思う。そう、ぼくも、本当に良かった。彼がいてくれて、本当に・・・