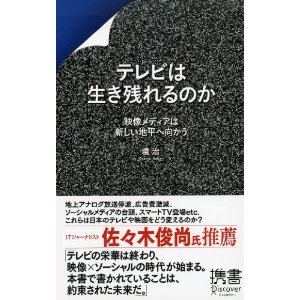もうみなさんご存じかもしれないけど。
ネット上の一部ではいま、かなりおぞましい言葉が飛び交っている。俳優の(そして宮崎あおいの夫)高岡蒼甫が、フジテレビの韓流ドラマ放送を批判するようなTweetをしてしまい、所属事務所を辞めた。これをきっかけに「フジテレビは韓流押しをしていてそこには裏があるのだ」という主張がネット上を駆け巡っているのだ。
このブログあたりを読むとだいたいの事情がわかる。また、Twitterで”フジテレビ”と検索すると生のTweetが読めるはず。ルサンチマンの塊みたいな痛々しい言葉が滝のように流れている。
そこにはいろんな想いが渦巻いているのだろうけど、感じるのは、ネット住民のマスメディアへの強烈な敵愾心だ。怨念とも言える。もともとマスメディアをマスゴミ呼ばわりしていたわけだけど、そこに”韓国がらみの陰謀”というネトウヨ的心性を刺激するモチーフも加わったもんで、かけ算というか累乗というか、爆発的なパワーを持ってしまった。攻撃対象が、”マスゴミ”の中でもっとも成功しているフジテレビだというのも、感情を逆撫でどころか何百回も掻きむしっている。
それにしても見ていると、ネット在住のみんなはそこまでテレビが嫌いなんだな憎いんだなと感じた。(それと、ソーシャルメディアは落ち着いたコミュニケーションの場だ、というのももはや過去の話なんだとも感じた。@higekuma3によれば震災後Twitterは2ちゃん化したのだとか)
さて一方、昨日ものすごく驚いたニュース。「民放5社が新たなインターネットテレビを来春に実用化、専用テレビも同時発売」ええええー?!な、な、なんですと!
テレビと大手広告代理店はネットを敵視し、また馬鹿にしてきた。ネットなんてあんなのメディアじゃない、と言っていたし、ネット上のコンテンツも、アマチュアが作るもんだと言っていた。それがどうも、大きく劇的に変わりそうだ。
テレビはスマートテレビを拒んでいたはずだけど、むしろ自分たちで作ろうと考えを大きく転換したのだろう。ネットに肩を貸すとテレビ放送の視聴率が奪われるという不安が彼らを脅かしていた。その不安は正しい。でも、どうやってもこうやっても、テレビはネットに視聴率を奪われる。だったら自分たちで考案した方が被害が少ないんじゃないか。そんな発想なんだろう。
なんにせよ、レガシーメディア側が新しいアプローチで挑んでいこうというのは、素晴らしいことだと思う。さあ、みんなよーいどん!で競争だぞ!そんな気分。
ところがね、記事をよーく読んでいくと、あれ?とも思う。このスマートテレビは、スマートじゃない。スマートテレビはネットにつながるのがミソだけど、このテレビはネットにつないでわざわざテレビ放送用のコンテンツしか視聴できないのだ。番組の二次市場を自分たちで作るのだけど、番組しか売らないからね、というスタンス。しかも”売る”わけ。
よーいどん!で競争・・・する気はやっぱりないんだな。おれたちの権益はおれたちが守り抜くぞー!という頑なさが相変わらず見える。これは決して、マスメディアとネットの融合、ではないな・・・
結局マスメディアはネットが嫌いなんだね。
ネット在住の”マスゴミ”論者は、2011年になってもやっぱりテレビを攻撃し続ける。対するマスメディアも結局はネットに泳ぎ出そうとはしない。お互いに閉じてしまっているようだ。
それではいかんのだよ。マスとネットが手を組むことで、それぞれの価値も拡大するの。だから君たち、仲良くしないといかんのよ。
・・・仲良くできないやつは、廊下で立ってなさい!・・・なーんてね・・・