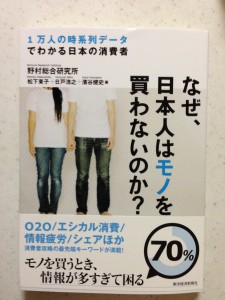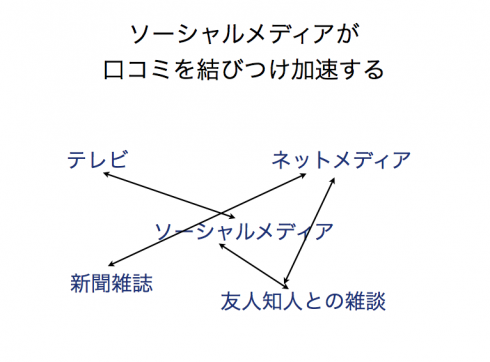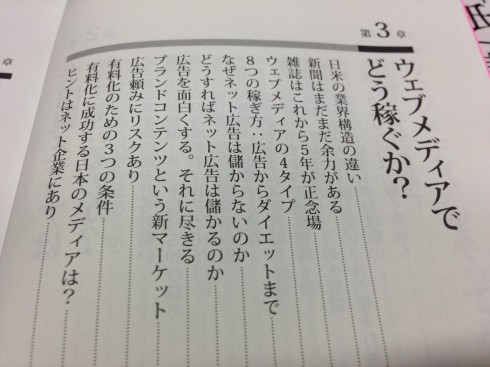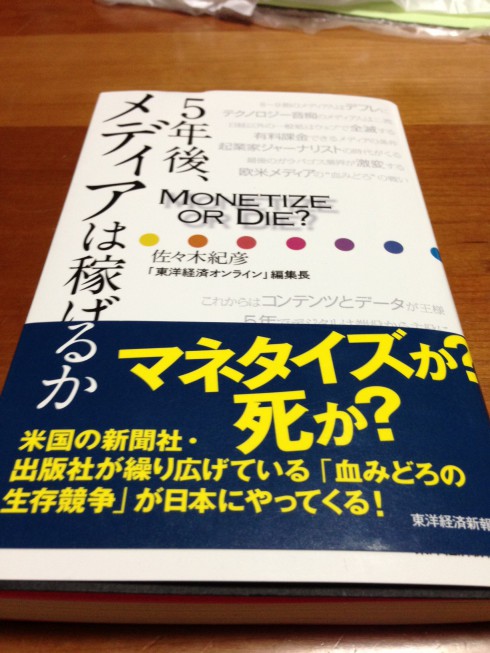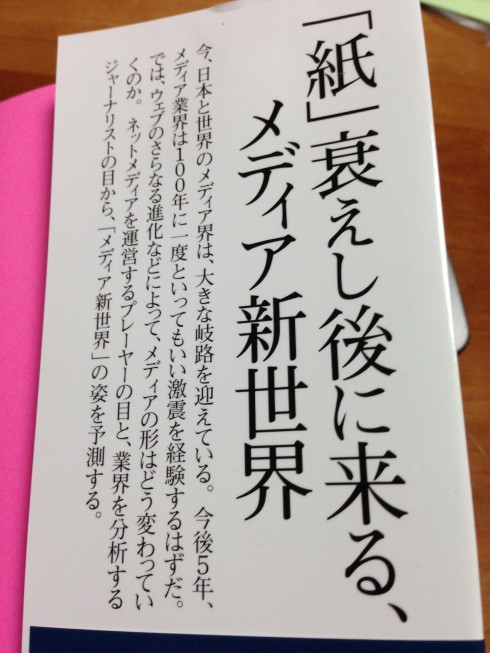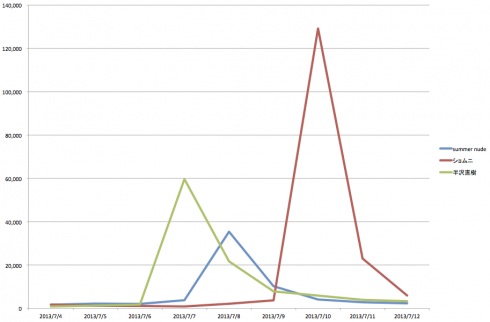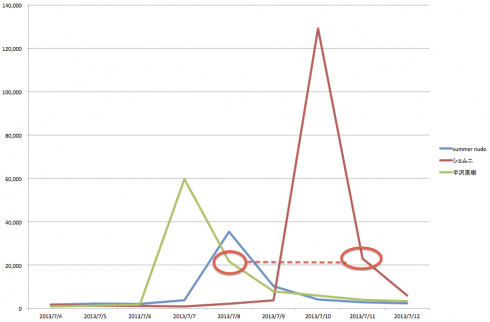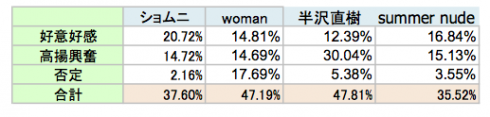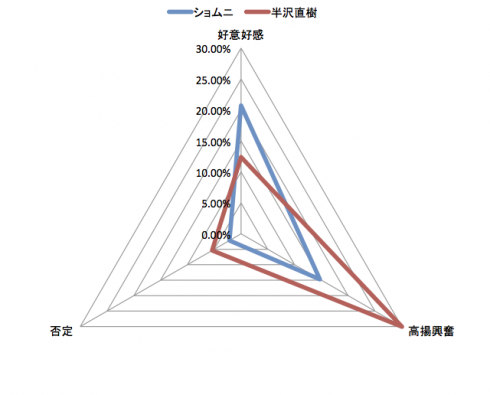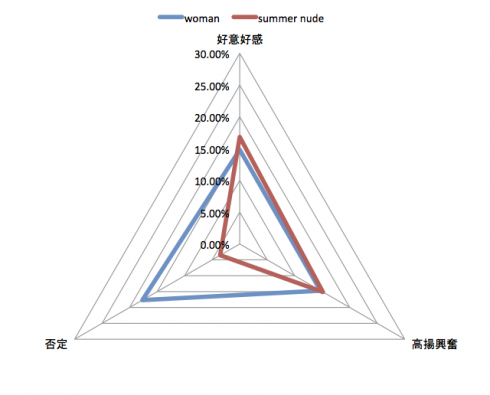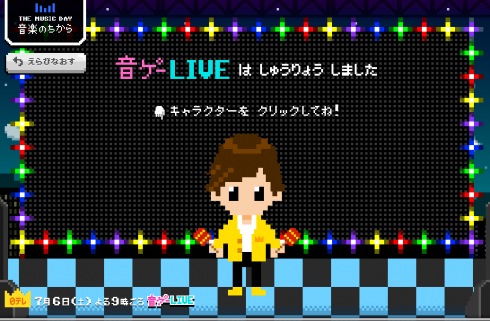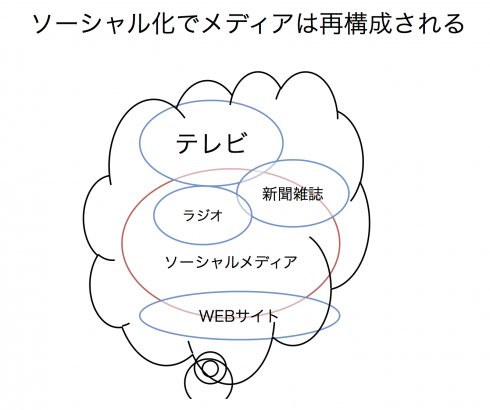宮崎駿監督のファンだったかって言うと、そこまでではないのだと思う。ただ、60年代生まれのテレビっ子世代は、意識しなくても宮崎駿の世界に接触してきた。
はっきり記憶しているわけではないが、最初にその名前を認識したのはたぶん、『ルパン三世 カリオストロの城』だったのだろう。この映画はルパン三世映画の二作目だった。一作目のクローンの話は、ものすごく楽しみに観に行ったのにあれ?という感じだった。別にダメな映画だったわけではないけど、ぼくの知ってるルパン三世じゃないぞ、と思えたのだ。
ぼくの知ってるルパン三世とは、最初のシリーズだ。コミカルでアクションも豊富で、エンタテイメント性抜群だった。ぼくはこれを何度も観た。当時は、人気の出た番組が何度も何度も再放送されたのだ。家族揃って観たものだ。楽屋落ちもけっこうあって、銭形が「ちくしょー、ルパンめー!来週こそ見てろよ!」と“来週“とわざわざ言ってトイレに入る、とか、ギャグのセンスがいいのだ。
映画第一作はそんなぼくの知ってるルパンと雰囲気がかなりちがった。峰不二子がルパンをぎゃふんと言わせたりアクションもこなすカッコいい女ではなく、かよわくてルパンに助けを求めてばかりなのが不満だった。こうじゃないんだけどなあ、ルパンは。中学生だったぼくにはフラストレーションが残った。
『カリオストロの城』はそんな第一作の不満をすっかり解消してくれた。好きだった最初のルパンのエッセンスがふんだんに撒かれて、さらに拡大したかのようだった。峰不二子もルパンたちの助っ人として登場しさらりと去っていった。そうそう、これがカッコいい不二子だよ。
『カリオストロ』は、最後だけはいただけなかった。銭形が、歯が浮くようなことを言うのだ。ルパンは何も盗まなかったというクラリスに、あなたの心を盗んだのだと言う。これはちがうだろう。銭形はあくまでルパンが憎いし心の底から逮捕したくて追い続けているはずだ。名シーンとしてとりあげられるこのラストは、ぼくからするとダメ出しすべきエンディングだ。
その『カリオストロ』のスタッフを調べたら、監督として宮崎駿とあった。最初のルパンのシリーズ後半に関わっていたらしい。家族みんなで大笑いして観ていたのは、この人のセンスだったんだな。さらに調べると、幼い頃に観た『長靴をはいた猫』『空飛ぶゆうれい船』『どうぶつ宝島』にも関わっていたと知った。そうだったのかー!高校生になっていたぼくはその名を胸に強く刻み込んだ。
『ナウシカ』『ラピュタ』の頃は大学生になっていた。『カリオストロ』の宮崎駿(ずーっと”しゅん”と読んでいたが)がオリジナル作品を映画にしたというので劇場に勇んで観に行った。『ナウシカ』の物語の底にあるエコ思想的な世界の捉え方は新鮮だった。
『ラピュタ』は当時つきあっていたフェミニズムを学んでいる女の子と観に行った。「アニメに行くの?」絵画好きでもある彼女が少し馬鹿にした感じで言う。あー、宮崎駿を知らないんだなあ。「まあ騙されたと思って観てよ。普通のアニメと違うから」きっと観たらわかるはずだ。
映画館を出て「面白かったろ?」と聞いたら「そお?」とまた鼻で笑う。「やっぱりアニメって絵が薄っぺらいのよねー」なんだと?!「それに女の子のキャラクターがステレオタイプなのよね。守られてるだけじゃない?」どこ観てんだー!・・・そこからは大げんかだった。
『ラピュタ』を観るたびにぼくは、けんかばかりしていたフェミニズムな彼女を思いだす。最後の呪文がバルスという言葉だったことなんかは憶えてないのに。その彼女とはけんかばかりしながら一年間付き合って別れた。その数年後、彼女は交通事故で亡くなってしまった。亡くなった一年後に知ったぼくは一晩中泣いた。そんなことまで『ラピュタ』は思い出させる。
その後、子供ができてからはその成長とともに宮崎アニメがあった。『トトロ』はご多分に漏れず、ビデオで何度も何度も、テープがすり切れるほど観た。幼児は気に入った作品を、何度も何度も観て飽きないのだ。
『紅の豚』は最初はよくわからなかった。どうして豚なのだ?でもこの豚は『カリオストロ』のルパンだと気づいた。この映画のキャッチフレーズは「カッコいいとは、こういうことさ。」だった。豚なのにカッコいい。宮崎アニメの男は豚か人間かは置いといて、同じ美学を持っている。武骨で不器用でプラトニック。でも決然と女性を守る。古典的な男だ。
『もののけ姫』は邦画の興行史を塗り替えるほどの大ヒットとなった。ぼくはこれは、トトロのおかげだと思う。我が家同様、テープがすり切れるほど『トトロ』を観た家族が、映画館におしかけたのだ。じゃなければ、あんな難解な映画が空前のヒットになるはずがない。
『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』までは家族で劇場に観に行った。だが『崖の上のポニョ』はもう子供たちが観たがらなくなっていた。宮崎アニメを、というより、アニメ映画そのものを卒業してしまったのだ。
『風立ちぬ』はぼくひとりで劇場で観た。宮崎駿映画を劇場で観るのは久しぶりだった。
ああ、そうかあ、と思った。ぼくたちは宮崎駿が描いた、美しいもの、を観ていたのだなあ。そうだよ、全部同じだ。ずっと、そうだった。『紅の豚』が少しわかった気がした。あの映画で豚が人間だったら、カッコよすぎだ。恥ずかしくなる。豚だからバランスがとれる。
それからすると、『風立ちぬ』はそんな”照れ”も吹っ切っているのかもしれない。恥ずかしげもなく、美しいものを次々に描き出し、並べていく。戦前、少年、少女、飛行機、青い空、純愛、はかない命、戦争、家族、敗北、崩壊・・・などなどなど。極めつけは二人の告白の場面。彼女の父親の前で、本人に確かめる前に「彼女を愛しています」と言ってのける。恥ずかしげもなさすぎて呆然とするしかない。
『風立ちぬ』が監督引退作なのは、だから仕方ないのだ。あれ以上恥ずかしいことはもうできないだろう。やりたいことをすべて凝縮してしまったんじゃないのか。
ぼくにとっても、もう宮崎駿はお腹いっぱいだ。だから引退会見を見ても、残念とは思わなかった。ごちそうさま、もう十分いただきました。そして、もうこれほど胸に刻むアニメ映画監督もないと思う。『長靴をはいた猫』を観て以来、ぼくのアニメ体験を導いてきた人なのだから。ぼくは宮崎駿のファンとは言えないと書いたけど、それにしてもずっと観続けても来た。ぼくの人生にはいつも宮崎アニメがあった。ファンじゃないけど、美しいもの、カッコいいとは何かを教えてくれた、親戚の叔父さんみたいなものだ。それは作家とファン以上の関係かもしれない。そしてそういう関係を宮崎駿と結んで生きてきた人はものすごくたくさんいるのだ、この国には。
そうか、そうやって考えていくとすごい人だなあ。宮崎駿さん、ありがとうございました!お疲れさまでしたー!
コミュニケーションディレクター/コピーライター/メディア戦略家
境 治
What can I do for you?
sakaiosamu62@gmail.com