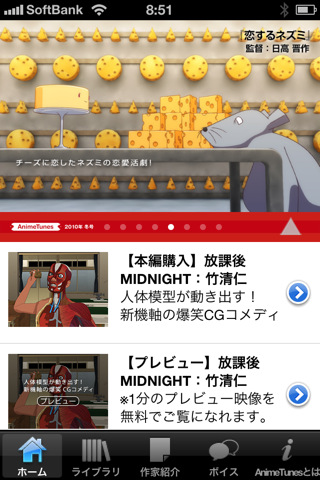映画『ソーシャルネットワーク』を公開日に鑑賞したことはこないだ書いたよね。みなさん続々観に行ってるみたいで、タイムラインで「面白かった!」というつぶやきをよく見る。ゴールデングローブ賞をとったこともプラスに働いてるだろう。
これから観に行く人のために書いておくと、パンフレットの質が高いので買うといいと思う。監督や脚本家のインタビューも充実してるし、佐々木俊尚さんの解説文もある。きわめつけは、mixiの人たちが社長以下3名登場して座談会やってる。まさにソーシャルネットワークそのものをきちんと説明しようとしている。
その中で面白かったところをぜひ書いておきたい。この物語は、Facebookの創業者マーク・ザッカーバーグと共同創業者エドゥアルド・サベリンの確執がメインになっている。けれども映画の中で、いがみ合いながらもお互いをいまでも親友だと思っているのではと感じさせる場面がある。
これについて、インタビュー記事の中の監督のデヴィッド・フィンチャーと脚本のアーロン・ソーキンの解釈が微妙にちがうのだ。その微妙な違いがそのまま映画ににじみ出て「思っているのでは」と感じられたのだろう。この映画はそんな風に、多面的、多重的に解釈できたり受け止められたりする。そこが面白さなんじゃないだろうか。
さてこの映画を観てから、ぼくもなぜだかFacebookに頻繁にアクセスするようになった。アカウントはもう一年ぐらい前につくってあったのだけど、ずーっとほったらかしてた。まったく何もしなかったわけでもなく、週に一度ぐらいはのぞきにいったり、お友達申請があったら承認したり、Twitterとつなげてみたりした。でも、「結局何をどうしたらいいかわからない」状態だった。
Twitterもそんな状態が3か月ぐらいあったから、ソーシャルメディアとはそんなものなのかしら?
それがどうして頻繁にアクセスするようになったのかというと、すごく単純な話で、お友達が盛んに活動するようになったからだ。お友達の数がいい頃合いで増えてきて(それでもまだ25人だけ)、その中で活発に発言する人が出てくると、ぼくの方も何か言いたくなったり、「いいね!」ボタンを押したくなったりする。そうすると、またレスポンスがあったりして、だんだんぼくの活動も活発になってくる。
そう言えばTwitterで活発にやりとりするようになったのも、似たようなことだった気がする。話しかけられるとこっちも話したくなる。”社交”メディアなのだから、当たり前かもね。
そこに気づくと、逆に使い方で戸惑ったポイントがわかった気がする。Twitterもやっている人は、Facebookとどう使い分けるか、指針を持った方がいい。ぼくはそこ、欠けていた。とくに、TwitterのつぶやきをFacebookにそのまま流し込んでいると、Facebookに参加している意味がぼやけてしまう。
Twitterをやってた人がFacebookもはじめると、この2つの接続のやり方が書かれたブログなんかがあって、そんなことできるのならつなげちゃおう、と、ついついやってしまうかもしれない。でも明確な意識なしにこれをやると、「じゃあおれってFacebookで何言えばいいんだっけ?」ということに陥ってしまう。というか、ぼくがそうだったのだけどね。笑
だから、Facebookわかんね、って人は、Twitterとの接続を外してみたらどうかな?
それからもうひとつ、Facebookでは「何をしたらいいかわからない」となってしまいがち。これについて、「インターフェイスが不親切だしかわいくもない」という意見をよく見る。確かにぼくも、何をしたらいいかわからないのは、インターフェイスのせいだと思っていた。
でもこれは、日本のITサービスに浸っているからかもしれない。
日本のITサービスは、いや、そもそもWEB全般は、メニューがものすごく多い。何をすればいいか、あっちこっちに書いてある。至れり尽くせり、なのかもしれない。アクセス解析の結果、ユーザーが迷わずにすむ設計をしたから、なのかもしれない。
でも、ゴチャゴチャしすぎてない?
で、べつに「何をしたいならここをクリック」などと表示しなくても、お友達が興味深いこと書いてるのを見たら「いいね!」ボタンを押せばいいのだ。ぼくの場合、そういう状態に自然になるまで時間がかかっただけのこと。インターフェイスの問題とは別だったんだ。
インターフェイスがかわいくなくたっていいんだ、ホントは。ソーシャルメディアのコンテンツは”お友達”なのだから、お友達の発言や活動なのだから。むしろ、デザインがゴチャゴチャしてる方が困るだろう。お友達がもたらした”フィード”がパッと目に入った方がいいのだ。
Facebookってよくわかんない、って人は、コツコツとお友達を増やせばいい。そしたらきっとある日、誰か面白い人が出てきて、あなたも何か言いたくなるから。
さて、Facebookは今年来るんじゃないか、いや結局は来ないんじゃないか、という議論があちこちで盛んだ。
ぼくの結論は、こう。
Facebookは今年、大きくユーザーを増やすぞ!
その理由は、「ぼくが使うようになったから」。
えらそうでしょ?(笑 でも、ぼくは”アーリーマジョリティ”だと思ってるの。決して、アーリーアダプターでもないし、ましてやイノベーターでもない。”大多数の中の早い方”がぼくだということ。そのぼくが頻繁に使い出した。だから、”大多数”が使いはじめるだろうと。
結構当たると思うよ。Twitterもそうだったしね!