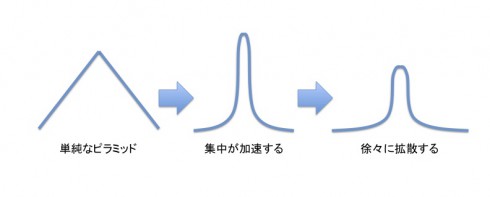さて、日本映画産業論と銘打ったからには、映画の話を中心に書いていくよ。でも、映画の話は他のすべてのコンテンツ産業とかなりからみあっているんだ。
で、ここで問題です。興行収入はどう還元されるか。例えば、興行収入20億円の作品があったとしよう。この20億円は、どう分配されるのかって話だよ。
20億円のうち、約半分は興行側、つまり劇場がとるんだぜ。ああそうですか、って思うだろうけど、小売りマージンが50%ってビジネスもそうそうないんじゃないかな。でも劇場は投資額が普通の小売業とは全然ちがって大きいから仕方ないかもしれない。実際、たくさんできたシネコンもここへ来て運営は厳しいらしいよ。やや過当競争になってきたし。
約半分は興行側がとると書いたけど、”約”ってのは、ちょうど半分ではないから。もう少し詳しく書くと、配給会社や作品によって半分じゃなかったりもする。配給会社が、次々にお客さんをよべそうな作品を提供してくれるなら、半分以下ってこともある。反対に、いつもあんまりお客さんを呼べないねえ、きみ、という配給会社だと、半分以上とらせてもらうよ、ってことにもなる。
ここは何しろビジネスだよ取引だよ、ということで、いわゆるひとつの”力関係”で取り分が決まるってわけ。これはまあ、どの産業でもそんなもんだろうよ。
さていま、配給会社と劇場側の関係で決まる、てなことを書いた。そう、配給会社なんだね、ここで劇場と交渉するのは。普通の商品で言うと”卸す”役割を配給会社がになう。配給会社はメーカーだと捉えれば、メーカーと小売りの関係と同じだとも言える。
話が長くなっちゃった。だから、20億円の興行収入は、劇場側が10億とるので、残りは10億だね。それが配給会社に渡るわけ。
配給会社は配給手数料をとる。30%から40%ぐらいだと言われている。これも、配給会社の力や姿勢でちがってくる。まあここでは30%だとしましょう。そうすると3億とることになるので、残りは7億だ。
それから、ここでA&P料を差引かれる。は?A&Pって何なのよ?
AはAdvertisementつまり、宣伝費だ。Pの方はPrint料つまり映画フィルムをコピーする費用。映画はマザーにあたるフィルムをプリントしてつまり複製して全国の映画館に送り届ける。それによってあなたの町の映画館でも上映されるわけ。
このA&P料はいくらぐらいだろう。これはケースバイケースだ。もちろん、あらかじめその映画に関わる人びとの間で「今回の作品はA&Pで○○億ぐらいは必要ですね」と共有はされている。AもPも配給会社の業務領域なので彼らが立て替えてたりする。それが差引かれる。
相当大ざっぱに、この作品のA&Pは2億円としておこう。20億のヒットになるような作品だと2億じゃ済まないんだけど、そんなこと言ってたらキリがないので2億としちゃう。
それでいくら残る?うーんと、さっき7億円だったから2億円差引くと5億円になるね。
あれ?最初は20億円だったのに、5億円になっちゃった。4分の1だよ。まあ、でもいいや、5億円も残ったぞバンザーイ。この5億円は”製作委員会”に戻ってくる。製作委員会はテレビ局とか出版社とか制作会社とか、もちろん配給会社も加わっている、言ってみればジョイントベンチャーだ。その複数社の委員会に5億円が戻ってきた。うれしいねえ!
おいおい、ちょっと待てよ。製作費はどうなってたっけ?えーっと、ああそうだ、5億円かかってたんだっけ・・・・あれ?
製作委員会に戻ってきたのが5億円。製作費は5億円。てことは、戻ってきて儲かったんじゃなくて、製作費分の元をとったってだけかよ、なんじゃそりゃ!
ここでもう一度整理しよう。興行収入20億円ー劇場10億円ー配給手数料3億円ーA&P料2億円=5億円
でもって、5億円ー製作費5億円=0円
うーん、日本映画で20億円といえば大ヒットなのに、最後は0円になっちゃうの?
知ってる人は知っての通り、実際にはこのあとDVDが出た時に利益が出るので、それではじめて”儲かった”ってことになる。
ここまで長くなっちゃったので、続きは次回。次は今週中に更新するよ。
とにかく、上で書いた構造というか計算方法というか考え方というか、今後の話の中で重要になるので憶えておいてね。そこには日本映画の問題の原点が潜んでいるから。暗記しとけよ。試験に出るぞ!