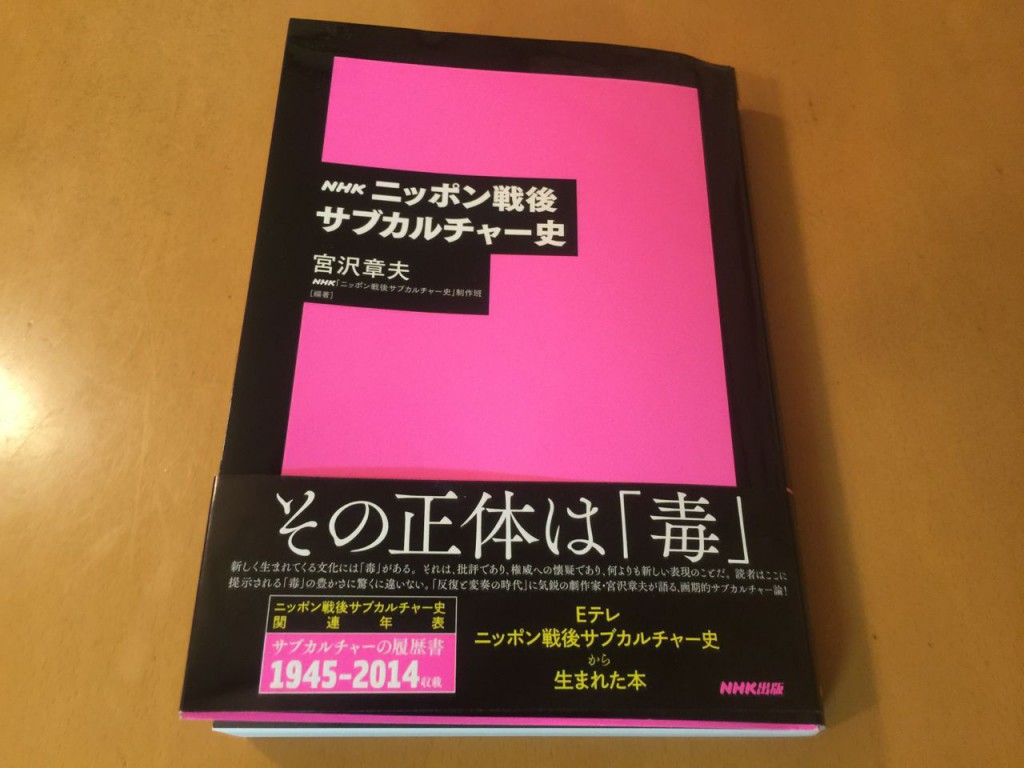
『ニッポン戦後サブカルチャー史』はNHK Eテレで2014年8月1日から毎週金曜日放送された、全10回の番組だった。
この番組は”講義形式”だったのだが、まず講師役を務めた宮沢章夫氏について語らねばならない。
語らねばならないというより、語りたい。ぼくはまず、この番組について書くにあたりどうしても、宮沢章夫氏に関して語りたくて仕方ないのだ。
宮沢氏は80年代に「ラジカル・ガジベリ・ビンバシステム」というキテレツな名前の演劇ユニットで喜劇の最高峰を極めた劇作家だ。ここで「喜劇の最高峰を極めた」と書いたのはまったくぼくの主観だ。それに実は、ぼくはさほど芝居をたくさん観てきたわけではない。だから比較対象が少ないのだが、他と比較する必要はないのだ。間違いなく、ラジカル・ガジベリ・ビンバシステムが80年代後半に原宿ラフォーレを中心とした舞台で繰り広げた一連の芝居は、最高峰の笑いを繰り広げた。少なくとも、あれほど笑ったことはない。
「抱腹絶倒」という言葉があるが、あとにも先にも、「抱腹絶倒」にふさわしい経験はラジカル・ガジベリ・ビンバシステム以外にはなかった。いや、ラジカル・ガジベリ・ビンバシステムを観て初めてぼくは「抱腹絶倒」の真の意味を知ったのだ。あれ以外に「抱腹絶倒」という形容をしてはならないとさえ思う。
そして、笑いを極めると、宗教に近づく。
85年から89年の最終公演まで、ほぼ半年に一回ほどの公演は、ぼくにとって教祖の講話を聞きに行くようなものだった。毎回、啓示を受け、解脱の境地に近づく。そんな思いだった。
そこでは、すべての価値観が相対化され、フラットになる。あるいは、既存の物語の語られ方、起承転結の類いを超越し、ただ短い瞬間だけが存在し弛緩してつながっている。”刹那”というのが何か、笑っている間はわかるのだ。
だから宮沢章夫氏は、神の使徒のような存在だ。啓示を伝え運んでくれる存在。民にもわかりやすくかみ砕いてくれる者。だから宮沢氏と呼ぶより、宮沢師と呼びたい。そんな宮沢師が講師を務める講座は、毎週観ないわけにはいかなかった。
イントロダクションが長すぎた。『ニッポン戦後サブカルチャー史』の話をしよう。
8月から、毎週この番組が放送された2カ月強の間はめくるめく至福の時間だった。しかも、これはなんという偶然か、いや何かの神様が仕組んでくれたとしか思えないのだが、同じ金曜日に7月から9月までテレビ東京で『アオイホノオ』というドラマが放送された。これがまた、80年代初頭の若者を描いたサブカルチャー史の一編のようなドラマだった。まるで、『ニッポン戦後サブカルチャー史』のサブテキストだった。かくして、23時からEテレを観たあと、12分間の休憩時間ののち、24時12分から『アオイホノオ』でさっきの講義の復習をするという、奇跡のように濃厚で幸福な時間を堪能できた。
『ニッポン戦後サブカルチャー史』の講義一覧を見てみよう。
第1回「サブカルチャーはいつ始まったか? 戦後〜50年代」
第2回「60年代新宿カルチャー/大島渚は何を撮ったのか? 60年代(1)」
第3回「劇画とナンセンスの時代〜「カムイ伝」と「天才バカボン」〜 60年代(2)」
第4回「深夜ラジオと音楽革命 70年代(1)」
第5回「雑誌ワンダーランド 70年代(2)」
第6回「What’s YMO〜テクノとファッションの時代〜 80年代(1)」
第7回「「おいしい生活」って何?〜広告文化と原宿・渋谷物語〜 80年代(2)」
第8回「セカイの変容~岡崎京子・エヴァンゲリオン・ゲーム~90年代(1)」
第9回「おたく→オタク→OTAKU 〜オタクカルチャーと秋葉原〜 90年代(2)」
第10回「サブカルチャーはどこから来て どこへ行くのか〜ゼロ年代〜現在」
ひと目で分かるように、10年ごとに年代を分けてサブカルチャー史を検証していっている。この番組の何に打ち震えるのかというと、60年代のガロや少年マガジンが学生紛争のバイブルになったことや、70年代の深夜ラジオが若者たちの解放区になったことなど、ここで取り上げられた主題はこれまでもあちこちで断片的に語られていた。それをこの番組では、一気に俯瞰して”通して”とらえようとしている。
サブカルチャーを50年代からゼロ年代まで一気通貫する、という発想。とらえ方。サブカルチャーにそんな見方があることを提示してくれた時点で、この番組は大きな仕事をしてくれたと思う。それだけでまず、大いなる価値があった。
そして、そこに大きな文化的価値が出てきそうなのは、例えば60年代生まれのぼくがサブカルチャーを分断して見ていたように、多くの人びとがその人なりの分断でサブカルチャーというものを見ていたはずだからだ。
番組の最後の方で宮沢師はサブカルチャーとカウンターカルチャーの相違点を言ってのけた。師とまで呼んだのに楯突くようなことを言うのだが、そこはちょっと違うと思う。昔のサブカルチャーは限りなくカウンターカルチャーに近かったとぼくは思うのだ。
ビートニク、太陽族、大島渚、新宿、カムイ伝、天才バカボン、ヒッピー、深夜ラジオ、日本語ロック、ホールアースカタログ・・・これらはすなわち、既存の価値観に反抗しアンチテーゼを突きつけるものだった。
それがピークを迎えるのが80年代だったのではないだろうか。それまでアンダーグラウンドとして扱われたサブカルチャーが突如水面の上まで浮上し、脚光を浴びた。暗がりで日の目を見ない存在だったのが、一躍表舞台に踊りだし、ついでに企業のお金も回ってくるようになった。それが広告文化だ。
広告そのものも黒子だったはずなのに脚光を浴びるようになり、アンダーグラウンドな者共は広告の舞台の上に引っ張り込まれてメジャーな文化の一端を担うようになった。
広告なら許される。広告になれば経済活動に参加できる。
え!?そんなのも有りになったの?それが80年代だった。
つまり、ニッポン戦後サブカルチャー史は、50年代に始まって80年代に大団円を迎えたのだ。ある意味、一回ゴールにたどり着いた。よくがんばったね!と褒められた。そして、さあ、次どこへ行こうかと相談していたらバブルがはじけた。がらがらがらっ。ゴールしたら、それでおしまいだった。それが、サブカルチャー史だった。
それでも、この国が続き、文化的な営みが続くのであれば、サブカルチャー史は継続していく。ただし、そこはつながっていないのだ。バブル以降にもサブカルチャーは連綿と生み出されるのだけど、その前のサブカルチャーとは脈絡ができていない。カウンターカルチャーではもうなくなっていた。アンチテーゼを突きつけるのではなく、もっと”逃げる”ような文化活動がサブカルチャーとなって表出した。(逃げるとの言い方は決して非難しているのではないのだけど)
だから『ニッポン戦後サブカルチャー史』は50年代から80年代までの”カウンターカルチャー編”と90年代以降の”メジャーな光から逃げる編”の2つに分かれているのだ、実は。
さっき書いた、この番組から『アオイホノオ』に連なる幸福も、そう考えると実に奥深い現象だったと言える。『アオイホノオ』は1980年代前半の大阪芸大が舞台だ。主人公・焔モユルは原作者・島本和彦の分身として漫画家をめざす熱い青年であり、彼が勝手にライバル視しているのはのちにガイナックスを結成して『新世紀エヴァンゲリオン』を制作する庵野ヒデアキらだ。実在の人物たちが実名で登場する。
彼らには”カウンターカルチャー”を担っていこうという意識はみじんもない。焔モユルは自分が大して絵が上手くないこともわかった上で、表現者としてのスターダムを駆け登りたい野心で頭がいっぱい。庵野ヒデアキに至っては素晴らしいアニメーションを完成させることしか頭になく、自分の動作にウルトラマンの効果音をつけたりする。世の中へのアンチテーゼどころか、自分たちの好きな世界への限りないリスペクトとピュアな探求心しか持っていない。
ぼくは彼らとほぼ同世代だが、彼らよりもずっとカウンターカルチャーに引きずられていて、東京に出てきた時も70年代のそうした動きの残骸を探して歩いたものだった。新宿に行けばアングラ劇団の足跡を探してみたし、植草甚一のエッセイを読んで銀座を歩いてみたりした。
だがいずれにせよ、庵野秀明たちがそうだったように、90年代以降のサブカルチャーの担い手は80年代までのカウンターカルチャーもおぼろげに知った世代だが、それとは分断された形で新しいものを形成してきた。
いまその分断を一気通貫で俯瞰することにはどういう意義があるのだろう。あっちのサブカルチャーとこっちのサブカルチャーは同じサブカルチャーだったのか!少なくともぼくはこの当たり前のことにあらためて気づかされた。
そこに気づくと、90年代以降のサブカルチャーをその前と分けて見ていたのが違う見方で見えてくる。あるいは、カウンターカルチャーのDNAめいたものが実はいまも生きているようにも思える。例えばスティーブ・ジョブズがMacに込めた哲学を一般化させたiPhoneは、つまりは70年代ヒッピー文化の21世紀的な具現化なのかもしれない。ヒッピー文化が思い描いた”自由”がこの小さなデバイスに結実したのかもしれないのだ。
そうかもしれないと気づいた時、また別のことに思い当たった。『ニッポン戦後サブカルチャー史』のプロデューサー・丸山俊一氏とは、少し交流があるのだが、彼は討論番組『新世代が解く!ニッポンのジレンマ』も制作している。奇しくも彼とは同年代(というか同い年)で、そんな彼があえて70年代以降生まれの討論番組をやっているのも面白いのだけど、そのこととサブカルチャーの分断を一気通貫することはどこか近い作業ではないだろうか。そして『ニッポンのジレンマ』は若い世代からアンチテーゼを突きつける番組だ。カウンターカルチャーと言えるかもしれない。同じプロデューサーがこの2つの番組に関わっていることは、ご本人さえ気づいていない重要な思いが潜在するのだろう。
テレビとは、戦後のメインカルチャーのど真ん中を歩んできた存在なのだが、周縁にサブカルチャーを合わせ持つことで新鮮さを保持してきたメディアでもある。それは例えば深夜番組という形で。80年代後半から90年代初頭のフジテレビの深夜番組はサブカルチャーのもっとも華やかな到達点と言えるだろう。いまやゴールデンタイムへの企画のお試しの場になった深夜帯だが、それでもなおテレビ東京を見ているとサブカルチャーの場の名残を感じる。そしてEテレも、発見している人にはサブカルチャーの重要な場のひとつになっている。
サブカルチャーはバブルとともに一度はじけたというのはぼくの世代だけが持つ勘違いと古い時代への郷愁にすぎず、それはちゃんと連綿と続いてきた。そしておそらく、カウンターカルチャーとしての矜持も表にはくっきり見えないけれど隠し持ちつづけてきたのだ。いつも爪を磨きながら隙あらばアンチテーゼを突きつけてやろうと機会をうかがっていた。
宮沢師によれば、サブカルチャーが生まれたのは師が生まれたのと同じ1956年だ。自分が生まれた年と同じというのは図々しいわけだが宮沢師が言うのだからそうなのだ。ということはまだ人間の一生分の歴史にも至っていない。還暦にもなっていない。
『ニッポン戦後サブカルチャー史』という希有な番組によってサブカルチャーを通史で検証したことは、このあとサブカルチャーは何をしでかそうというのかを見据えるための準備になった。あるいはぼくたちがもう一度サブカルチャーと自分の関わりをとらえ直す機会になった。そしてさっきからくどくど回りくどく”サブカルチャーにはカウンターカルチャーの意志が脈々と流れている”と言っているように、サブカルチャーには重要なミッションがあることを期待している。それはアンチテーゼの集大成であり、言ってみれば次の時代のメインとなる理念を生み出すことだ。そこまでやってサブカルチャーの通史が完了し、その一生は完成する。
もしそこにほんとうのゴールがあるのなら、ネット上のあちこちで、つまり周縁の場のさらにはじっこでもじゃもじゃ何やら発信しているみんなの力も、そこに向かっていけばいいのではないか。こうしてサブカルチャーについてブログでもごもご書いていることも、そこにみんなが向かう助けになればいいと思う。
とかなんとか体裁のいいことも言ってみているが結局この文章は『ニッポン戦後サブカルチャー史』に興奮して何か意義ありそうなことを書いておきたかったに過ぎない。あの番組へのリスペクトを持ちつつ、少しでも関わった感覚を自分で持ちたかったのだ。そんな駄文に最後までつきあってくれたそこのあなたに、サンキューと言っておきたい。
※Facebookページ「ソーシャルTVカンファレンス」ではテレビとネットの融合について情報共有しています。

コピーライター/メディアコンサルタント
境 治
What can I do for you?
sakaiosamu62@gmail.com
@sakaiosamu
Follow at Facebook
関連記事